検索フォーム
- 水の入ったコップ

- 2008年08月16日03:13
コップに水が入っている、というのは、どういうことだろう。

3歳

4歳

5歳

6歳
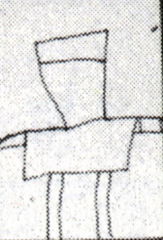
7歳
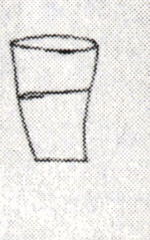
8歳
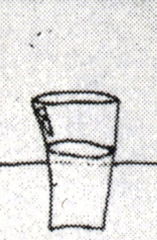
9歳

10歳

11歳
コップに水が入っている現象を目のあたりにしたとき、ガラスに囲まれてこぼれないまま口に運べる水の状態に、強烈な驚きがある、はずだ。
ものごとの理解が深まると、その仕方でしか理解できなくなり、ほかの理解の仕方を考えることすらできなくなる、ということはよくある。発達という概念もその二面性で考えると、進むと同時に後退する過程である。コップの絵にも、その二つの流れがある。
コップを斜めから見た図は、網膜への投射を写している。
それは、ほかの人の網膜にも投射されるべき映像だ。絵の上達とは、伝達しうる絵が描けるようになることを言う。絵は、よりよく見ることではなく、よりよく伝わることを目指しはじめる。3歳児のコップは、コップでないものにも見えてしまうが、11歳のコップは、誰にとってもコップでしかありえない。
子どもは、絵を描く技術が未発達で、描くメソッドも、道具を操るノウハウも蓄積していない。それはきっとその通りなのだが、実は3歳児も経験を描く技術に長けていて、年齢を重ねるごとに、その技術は薄れていく。
子供の描く絵を考えた本は、何冊か持っていたのだけれど『子どもの絵は何を語るか』(東山明・東山直美著 NHKブックス)を見逃していて、今日ブックオフで偶然手に入れた。この本に紹介されている調査がすばらしい。「皿とリンゴ」「コップと水」「サイコロ」「食卓と食べる人」といった共通したテーマで、3歳から11歳までの子どもを対象に、14000点もの絵を描かせたのだそうだ。本には、あまりに小さい図版がわずかに載っているだけなのが残念。スキャナで一部を拡大してみた。
発達心理学などの立場でこの資料を語ること自体、抜け出しづらい深みなのだと思う。なんの学問的立場にもよらず、子どもの描く形だけ見ていると、絵のきらめきを阻害しているのは、ほかならぬ「目」であることがわかる。

3歳

4歳

5歳

6歳
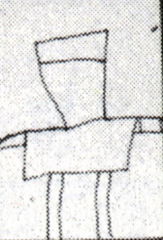
7歳
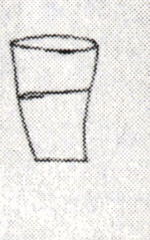
8歳
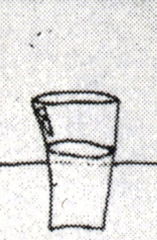
9歳

10歳

11歳
コップに水が入っている現象を目のあたりにしたとき、ガラスに囲まれてこぼれないまま口に運べる水の状態に、強烈な驚きがある、はずだ。
ものごとの理解が深まると、その仕方でしか理解できなくなり、ほかの理解の仕方を考えることすらできなくなる、ということはよくある。発達という概念もその二面性で考えると、進むと同時に後退する過程である。コップの絵にも、その二つの流れがある。
コップを斜めから見た図は、網膜への投射を写している。
それは、ほかの人の網膜にも投射されるべき映像だ。絵の上達とは、伝達しうる絵が描けるようになることを言う。絵は、よりよく見ることではなく、よりよく伝わることを目指しはじめる。3歳児のコップは、コップでないものにも見えてしまうが、11歳のコップは、誰にとってもコップでしかありえない。
子どもは、絵を描く技術が未発達で、描くメソッドも、道具を操るノウハウも蓄積していない。それはきっとその通りなのだが、実は3歳児も経験を描く技術に長けていて、年齢を重ねるごとに、その技術は薄れていく。
子供の描く絵を考えた本は、何冊か持っていたのだけれど『子どもの絵は何を語るか』(東山明・東山直美著 NHKブックス)を見逃していて、今日ブックオフで偶然手に入れた。この本に紹介されている調査がすばらしい。「皿とリンゴ」「コップと水」「サイコロ」「食卓と食べる人」といった共通したテーマで、3歳から11歳までの子どもを対象に、14000点もの絵を描かせたのだそうだ。本には、あまりに小さい図版がわずかに載っているだけなのが残念。スキャナで一部を拡大してみた。
発達心理学などの立場でこの資料を語ること自体、抜け出しづらい深みなのだと思う。なんの学問的立場にもよらず、子どもの描く形だけ見ていると、絵のきらめきを阻害しているのは、ほかならぬ「目」であることがわかる。